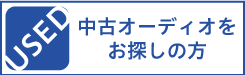marantz リファレンスオーディオの新基準 MODEL 10/SACD 10 展示しました!
マランツブランドとしてのトップエンド・プリメインアンプであるMODEL 10と、トップエンドSACDプレーヤーであるSACD 10を新たに展示いたしました。
それにしても、MODEL 10が税込定価2,420,000円で、SACD 10が税込定価1,980,000円と、かなりの高額商品ということで「ずいぶん思い切った商品戦略だなあ!」と驚いてしまいました。
マランツ史上初めてのウルトラハイエンド製品ということになりました。
この10シリーズのカタログによると、この2機種は「Reference Integrated Amplifier」と「Reference SACD Player」というネーミングで掲載されておりました。
趣味のオーディオ機器の製品ラインナップは、国内外とも高級化が進んでおります。そんな中でアンプやCDプレーヤーの高級品はセパレート化した製品が多いのですが、今回マランツが選択したのが「一体型」の製品でした。
これは私が思うには、従来のハイエンドオーディオに慣れ親しんできたユーザー層ではなく、新しく高級オーディオに興味を持って入ってこられたユーザー向けに、「クオリティはハイエンドでありながら、2ボディで収まる、使い勝手の良い製品」を選んだのではないかと思います。
その一方で、メーカー側にしてみれば、プリメインアンプという1台で完結した製品とすることで、「設計の自由度」が増して、信号経路の短縮化を実現し、より効率の良い突き詰めた製品に仕上げることができるというメリットがあったようです。
ハイエンドオーディオの世界は、楽しまれてきたお客様の高齢化が進んでおり、その次の世代の方々にとっては、スペース的・金額的の面でもダウンサイジング化が求められているように思います。そいう意味ではハイエンド・プリメインアンプとハイエンド一体型SACDプレーヤーという組み合わせは、今後も増えていきそうな予感がしてきます。
それでは個別に商品を見ていきましょう。
その前に、感じたことがあります。この製品を手に取って思ったことは、サイズの割に非常に重く感じることでした。スペックでは両機種とも33㎏くらいと、めちゃくちゃ重いと感じる重量ではないと思うのですが、実際手に取ると非常に重く感じるのです。これは、ただ単に私が年を取って筋力が無くなったせいなのか、それともサイズの割に重量が重いのか、よくわからないのですが、確かに重く感じます。お年を召されていらっしゃる方は、無理をしないで慣れている方に手伝ってもらった方がよろしいかと思います。
それにしても、MODEL 10が税込定価2,420,000円で、SACD 10が税込定価1,980,000円と、かなりの高額商品ということで「ずいぶん思い切った商品戦略だなあ!」と驚いてしまいました。
マランツ史上初めてのウルトラハイエンド製品ということになりました。
この10シリーズのカタログによると、この2機種は「Reference Integrated Amplifier」と「Reference SACD Player」というネーミングで掲載されておりました。
趣味のオーディオ機器の製品ラインナップは、国内外とも高級化が進んでおります。そんな中でアンプやCDプレーヤーの高級品はセパレート化した製品が多いのですが、今回マランツが選択したのが「一体型」の製品でした。
これは私が思うには、従来のハイエンドオーディオに慣れ親しんできたユーザー層ではなく、新しく高級オーディオに興味を持って入ってこられたユーザー向けに、「クオリティはハイエンドでありながら、2ボディで収まる、使い勝手の良い製品」を選んだのではないかと思います。
その一方で、メーカー側にしてみれば、プリメインアンプという1台で完結した製品とすることで、「設計の自由度」が増して、信号経路の短縮化を実現し、より効率の良い突き詰めた製品に仕上げることができるというメリットがあったようです。
ハイエンドオーディオの世界は、楽しまれてきたお客様の高齢化が進んでおり、その次の世代の方々にとっては、スペース的・金額的の面でもダウンサイジング化が求められているように思います。そいう意味ではハイエンド・プリメインアンプとハイエンド一体型SACDプレーヤーという組み合わせは、今後も増えていきそうな予感がしてきます。
それでは個別に商品を見ていきましょう。
その前に、感じたことがあります。この製品を手に取って思ったことは、サイズの割に非常に重く感じることでした。スペックでは両機種とも33㎏くらいと、めちゃくちゃ重いと感じる重量ではないと思うのですが、実際手に取ると非常に重く感じるのです。これは、ただ単に私が年を取って筋力が無くなったせいなのか、それともサイズの割に重量が重いのか、よくわからないのですが、確かに重く感じます。お年を召されていらっしゃる方は、無理をしないで慣れている方に手伝ってもらった方がよろしいかと思います。
MODEL 10の筐体内部は1.2mm鋼板で上下に仕切った2フロア構成で、上層をプリアンプに割り当てています。回路規模は往年の名プリアンプ「SC7」に匹敵するようですが、当然のことながら中身は一新しており、新設計のHDAMと進化型のHDAM-SA3を用いた可変ゲイン型回路を導入しています。ウェイブド・トップ・メッシュ越しに見えるのはケースに格納されたプリ専用のトロイダル型電源トランスです。プリアンプおよび左右のパワーアンプそれぞれ専用の強力な電源回路を搭載しています。
MODEL 10においては超高域までの優れたチャンネルセパレーションや音の実在感、そして広大かつ安定した空間表現の実現のためにフルバランス構成を採用しています。またボリウムコントロールには、高精度なステレオボリウムコントロールICと高音質化された最新型の「HDAM + HDAM-SA3」による電圧帰還型アンプ回路で構成された「リニアコントロール・ボリウム」を搭載しました。
下段のパワーアンプ回路は完全バランス設計を貫き、左右同一のデュアルモノ・シンメトリカル構成を採用したクラスDアンプを採用。デンマークのPURIFI(ピューリファイ)社と共同開発したスイッチングアンプはマランツ独自仕様で、出力はマランツのプリメインアンプ史上最大の片チャンネルあたり500W(4Ω)の出力を誇ります。
MODEL 10においては超高域までの優れたチャンネルセパレーションや音の実在感、そして広大かつ安定した空間表現の実現のためにフルバランス構成を採用しています。またボリウムコントロールには、高精度なステレオボリウムコントロールICと高音質化された最新型の「HDAM + HDAM-SA3」による電圧帰還型アンプ回路で構成された「リニアコントロール・ボリウム」を搭載しました。
下段のパワーアンプ回路は完全バランス設計を貫き、左右同一のデュアルモノ・シンメトリカル構成を採用したクラスDアンプを採用。デンマークのPURIFI(ピューリファイ)社と共同開発したスイッチングアンプはマランツ独自仕様で、出力はマランツのプリメインアンプ史上最大の片チャンネルあたり500W(4Ω)の出力を誇ります。
また、プリメインアンプの中で最も繊細な信号を扱うフォノイコライザー基板は、1.2mmのボトムケースと銅色にアルマイト処理されたアルミニウム製のトップカバーでシールドされており、外来のノイズによる音声信号への影響を排除しています。
また電源回路においても、独立したプリアンプ専用電源回路と、二つのパワーアンプ用スイッチング電源回路を搭載して、回路間及び左右チャンネル間の相互干渉を徹底的に排除して、セパレートアンプに匹敵する低歪みとチャンネルセパレーションを実現しました。
フォノイコライザーアンプは、MM/MC両方のカートリッジに対応する「Marantz Musical Premium Phono EQ」を搭載して、20dBのゲインのMCヘッドアンプと、40dBのゲインのHDAM+HDAM+HDAM-SA3の無帰還型フォノイコライザーアンプの2弾構成にすることによって、1段あたりのゲインを抑え、低歪みを実現しています。
このプリメインアンプには、MODEL 10をもう1台使ってモノラル駆動させる「コンプリート・バイアンプ駆動」(価格も倍の4,840,000円!) もできるようですが、ファイルウェブの試聴レポート等によると、音場空間が1.5倍ほどに広がったり、再生空間の再現性にかなりの違いが出るようです。当店には残念ながら1台しかありませんが、機会があったら是非試してみたいと思います。
また電源回路においても、独立したプリアンプ専用電源回路と、二つのパワーアンプ用スイッチング電源回路を搭載して、回路間及び左右チャンネル間の相互干渉を徹底的に排除して、セパレートアンプに匹敵する低歪みとチャンネルセパレーションを実現しました。
フォノイコライザーアンプは、MM/MC両方のカートリッジに対応する「Marantz Musical Premium Phono EQ」を搭載して、20dBのゲインのMCヘッドアンプと、40dBのゲインのHDAM+HDAM+HDAM-SA3の無帰還型フォノイコライザーアンプの2弾構成にすることによって、1段あたりのゲインを抑え、低歪みを実現しています。
このプリメインアンプには、MODEL 10をもう1台使ってモノラル駆動させる「コンプリート・バイアンプ駆動」(価格も倍の4,840,000円!) もできるようですが、ファイルウェブの試聴レポート等によると、音場空間が1.5倍ほどに広がったり、再生空間の再現性にかなりの違いが出るようです。当店には残念ながら1台しかありませんが、機会があったら是非試してみたいと思います。
SACD 10はディスク再生に照準を定めた妥協のないディスクプレーヤーで、現行最上位のSA-10から格段の進化を遂げています。MODEL 10同様、筐体構造は堅固をきわめ、フロントとサイドパネルだけでなくトップカバーにも分厚い削り出しアルミ材を配して共振対策を徹底しました。
マランツオリジナルのディスクリートDAC「Marantz Musical Mastering」の最新バージョンを搭載し、オリジナル・メカエンジン「SACDM-3」採用、アナログ/デジタル完全独立電源回路、マランツサウンドの特徴の一つである、どこまでも広がるようなナチュラルな空間表現を実現するために、非磁性体のアルミニウムトップカバーを採用。12mmの厚さを持ち、ボディ全体の高剛性化に貢献しています。
マランツオリジナルのディスクリートDAC「Marantz Musical Mastering」の最新バージョンを搭載し、オリジナル・メカエンジン「SACDM-3」採用、アナログ/デジタル完全独立電源回路、マランツサウンドの特徴の一つである、どこまでも広がるようなナチュラルな空間表現を実現するために、非磁性体のアルミニウムトップカバーを採用。12mmの厚さを持ち、ボディ全体の高剛性化に貢献しています。
内部構造はMODEL 10と同様の2フロア構成で、重量級の3層ボトムシャーシの上にメカドライブとアナログ・デジタル完全独立構成の電源回路を配置。上層にはデジタル基板とディスクリートDAC「Marantz Musical Mastering(MMM)」を独立した基板配置で構成しています。
MMM以降のアナログ回路は、ハイスピードで情報量豊かなサウンドのために、フルバランス・ディファレンシャル構成のオーディオ回路を採用しました。全てをディスクリート回路で構成して、パーツも厳選して一切妥協のないアナログオーディオ回路を実現しました。設計技術の進化とサウンドマスターによる精密なチューニングにより、マランツサウンドをかつてないほどピュアに表現しています。その結果、リスナーはかつてないほどのディティールを体験することができます。
またSACD 10は、USB-AおよびUSB-B端子経由で11.2MHz DSD およびPCM 384kHz / 32bitをサポートします。また、192 kHz / 24bitに対応する同軸および光デジタル入出力も装備しています。
MMM以降のアナログ回路は、ハイスピードで情報量豊かなサウンドのために、フルバランス・ディファレンシャル構成のオーディオ回路を採用しました。全てをディスクリート回路で構成して、パーツも厳選して一切妥協のないアナログオーディオ回路を実現しました。設計技術の進化とサウンドマスターによる精密なチューニングにより、マランツサウンドをかつてないほどピュアに表現しています。その結果、リスナーはかつてないほどのディティールを体験することができます。
またSACD 10は、USB-AおよびUSB-B端子経由で11.2MHz DSD およびPCM 384kHz / 32bitをサポートします。また、192 kHz / 24bitに対応する同軸および光デジタル入出力も装備しています。
ここからはいよいよ試聴です。
どのジャンルの音楽を聴いても、クリアな音像と滲みのない繊細な音が印象的でした。
さすがに両機種とも200万円クラスのハイエンドモデルですので、「一皮むけた」解像度の高い音楽が楽しめました。音楽の「密度」というかリアリティが素晴らしく、SACDプレーヤーとプリメインアンプの組合せでこのクオリティはやはり並みの製品ではないなという感じがしました。
➀ 五嶋みどり 「 ENCORE ! 」
クリアーな音場の中で滑らかなバイオリンの音色が心地良かったです。
➁ 水橋 孝(b) / 田中裕士(p) 「 Mr. BOUJANGLE 」
澄み切った空気感の中で、緻密なサウンドが印象的でした。
➂ Corrinne May 「 FLY AWAY 」
解像度の高い空間で、ヴォーカルの滑らかさが際立ちました。
➃ Arne Domnerus 「 Over The RAINBOW 」
ジャズライブハウスの独特の空気感とノリの良さが素晴らしいです。
➄ Crème de la Crème 「THE HIGHER YOU RISE」
フュージョンミュージック独特のノリの良いクリアなサウンドが楽しめました。
さすがに一般のSACDプレーヤーとプリメインアンプの組合せと比べると、価格もさることながら、そのクオリティの高さは思わず笑ってしまうほどの違いがありました。
価格的には、かなりの高級品ということになりますが、ハイエンドオーディオの世界の可能性を広げる、かなりの意欲的な製品と言えると思います。
こうした製品が出てくると、なるべく機材の数を少なくして、シンプルな組み合わせにしたいというご要望は一定数あると思いますので、選択肢が増えるという意味では良いことであると思います。
ただ前回のブログでも申し上げましたが、これからオーディオの世界に入ってこようとする方々にとって、ちゃんと価格的段階を経て、どの方向にも行けるように適切な選択肢を用意してあげることが、この業界にとって一番重要なことではないかと思ってしまいます。
どのジャンルの音楽を聴いても、クリアな音像と滲みのない繊細な音が印象的でした。
さすがに両機種とも200万円クラスのハイエンドモデルですので、「一皮むけた」解像度の高い音楽が楽しめました。音楽の「密度」というかリアリティが素晴らしく、SACDプレーヤーとプリメインアンプの組合せでこのクオリティはやはり並みの製品ではないなという感じがしました。
➀ 五嶋みどり 「 ENCORE ! 」
クリアーな音場の中で滑らかなバイオリンの音色が心地良かったです。
➁ 水橋 孝(b) / 田中裕士(p) 「 Mr. BOUJANGLE 」
澄み切った空気感の中で、緻密なサウンドが印象的でした。
➂ Corrinne May 「 FLY AWAY 」
解像度の高い空間で、ヴォーカルの滑らかさが際立ちました。
➃ Arne Domnerus 「 Over The RAINBOW 」
ジャズライブハウスの独特の空気感とノリの良さが素晴らしいです。
➄ Crème de la Crème 「THE HIGHER YOU RISE」
フュージョンミュージック独特のノリの良いクリアなサウンドが楽しめました。
さすがに一般のSACDプレーヤーとプリメインアンプの組合せと比べると、価格もさることながら、そのクオリティの高さは思わず笑ってしまうほどの違いがありました。
価格的には、かなりの高級品ということになりますが、ハイエンドオーディオの世界の可能性を広げる、かなりの意欲的な製品と言えると思います。
こうした製品が出てくると、なるべく機材の数を少なくして、シンプルな組み合わせにしたいというご要望は一定数あると思いますので、選択肢が増えるという意味では良いことであると思います。
ただ前回のブログでも申し上げましたが、これからオーディオの世界に入ってこようとする方々にとって、ちゃんと価格的段階を経て、どの方向にも行けるように適切な選択肢を用意してあげることが、この業界にとって一番重要なことではないかと思ってしまいます。